こんにちは、きぬまめです。
繊細さんとは、アメリカの心理学者エレイン・アーロン博士が提唱した、
HSP(Highly Sensitive Person)という概念がベースとなっている、
簡潔に言えば「とても感受性が強い人」。
きぬまめ自身も以前カウンセラーさんから、HSPであると言われました。
今回は、HSPカウンセラーである武田友紀さんが書かれた、
「気がつきすぎて疲れる」が驚くほどなくなる「繊細さん」の本をご紹介したいと思います。
この記事は次のような方に特にオススメです。
- ストレスを感じやすく、すぐに疲れてしまう方
- 繊細な感性を大切にしたまま、元気に生きていきたい方
繊細さは生まれ持った気質
「生まれつき繊細な人」は5人に1人の割合で存在するそうです。
しかも、繊細さは単なる気にしすぎではなく、繊細さんの脳の神経システムが刺激に反応しやすいことが分かってきました。
小さなことを気にしすぎて毎日疲れていたけれど、脳の神経システムが原因で感じる力が強いんだ、自分のせいではないんだと思うと心が少し軽くなりました。
繊細さんの心の仕組みを武田友紀さんは次のように表現しています。
繊細な感覚がせん毛のように伸びていて、相手の感情から音、光まで様々なものをキャッチする。繊細な感覚に触れたものが心や体に届き、心でじんわり味わう。
自分にとって「いいもの」も「痛い・つらいもの」も繊細な感覚で人一倍キャッチするのが繊細さんなのです。
繊細さんの悩みには共通点がある
感受性の強い繊細さんの悩みには「人といると疲れる」「仕事で効率を求められることが苦手」など、様々な悩みがあります。
そんな無数の悩みにも共通点があるそうです。
それは、「気づいたことに半ば自動的に対応し、振り回されている」ということ。
きぬまめは、「感情」と「行動」は切り離して考えるように、よくカウンセラーから言われてきました。
つまり、感じたこと(気づいたこと)をそのまま行動に移さずに、一旦どう行動するか(または行動しないか)考えてから、反応しなさいということです。
武田友紀さんも同様のことを述べられています。
繊細さんが元気に生きるためには、この自動応答を切ることが必要です。気づいたときにわずかでも踏みとどまって「私はどうしたいんだっけ?」と自分に問いかけ、対応するかどうか、また対応するならその方法を、自分で「選ぶ」ことが必要なのです。
感じる力が強い繊細さんは、まわりの人のニーズや世間の声に影響を受けやすいので、自分の本音を確かめることは非常に重要です。
「私はこうしたい」という自分の本音を大切にできた時、はじめて繊細さんは自分らしく元気に生きる切符を手に入れることができるのです。
繊細さんがストレスを防ぐ工夫
周囲が気になりやすく、時に幻聴などもあるきぬまめは、できるだけ周囲の音が聞こえないように、普段は可能な限りイヤホンをして音楽を聞いています(仕事中は無理ですが)。
武田友紀さんはイヤホンなど「物理的に」刺激から自分を守る方法を、「五感別」に提案なさっています。
五感(視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚)のうち、どの感覚が鋭いかは、人によって異なるそうです。
きぬまめの場合は断然聴覚が鋭いです。次は視覚だと思います。
例えば、聴覚に対する刺激の予防法は「耳栓をする」、視覚の場合は「メガネやコンタクトの度を落とす」などがあるそうです。
予防法に加えて、武田友紀さんは刺激を受けてしまった場合のケアの方法も提案されています。
例えば、聴覚なら「静かな場所で休む」、視覚なら「アイマスクをする」などです。
予防とケアをしながら、ストレス(刺激)からできるだけ自分を守りましょう。
繊細さんが人間関係を楽にする考え方
「人間関係を楽にできたら」、若い頃のきぬまめは常に人間関係に悩んでいました。
40代も後半になって、やっと少し落ち着いてきたように思います。
武田友紀さんは人間関係を楽にする根本的な考え方について次のように仰っています。
自分が当たり前に持つ感覚が、相手には「ない」のではないか?
繊細さんにはぜひこの疑問を持ってほしいのです。
それだけで、他者の見え方が大きく変わってきます。
繊細さんと非・繊細さんの感覚の違いは、繊細さんの想像をはるかに超えています。
もっと早く、この考え方を知っていたら、精神疾患を発症せずに済んだのではないかと悔やまれます。
不要なすれ違いが生じ、誰も悪くないのに傷つかないためにも、ぜひ知っておきたい考え方ですね。
それでは、繊細さんは非・繊細さんとどう付き合っていけばよいのか?
ズバリ、相手が察するのを待つのではなく、やってほしいことを言葉ではっきり頼む必要があります。
感覚とは価値観や考え方の土台になるもの。
人はそれぞれ感じ方が違うということをいつも念頭に置いて、
自分の想いを優しく言葉で伝えることができれば、たとえ理解してもらえなかったとしても、
最善は尽くしたと言えるのではないでしょうか。
繊細さんが安心して働くスキル
きぬまめは一般企業の障害者枠で事務職として働いておりますが、病気が悪化しないように、
会社からは常に自分のペースで無理をしないで働くよう言われております。
そんな恵まれた環境でも、常に業務量の多さや周りの雰囲気を感じとっては焦り、
1日が終わるころにはぐったりと疲れてしまいます。
そんな問題を解決するにはどうしたらよいのでしょうか?
武田友紀さんは繊細さんが仕事で消耗するのは体よりも「頭」だと仰っています。
「考え疲れ」や「緊張疲れ」があると神経が休まらず、疲れがとれにくくなるそうです。
実はその背景には不安があるため、安心感を増やすことでこれらの疲れを減らしていくことが最大のポイントだそうです。
例えば、繊細さんは丁寧な仕事をするためにマルチタスクが苦手な傾向にあります。
「全部終わらなかったらどうしよう」「どれから手をつけよう」と、
優先順位をつけることが苦手なきぬまめはマルチタスクを求められると不安でいっぱいになります。
そんな時、武田友紀さんは「一つひとつやっていこう!」を合言葉にしようと仰っています。
安心感がぐっと増えますね。繊細さんはひとつの仕事に集中して丁寧に仕上げることが得意ですから。
きぬまめのように優先順位をつけることが苦手な人は、無理に優先順位をつけずに、
「重要なものをひとつだけ選ぶ」ようにとも、武田友紀さんは仰っています。
もしこの方法でやっても終わらない場合、次のように考えるとよいです。
もしこの方法でやっても終わらないのであれば、それは、自分ができる仕事量を超えているということ。上司に相談する、同僚に手伝ってもらうなど、他の人の力を借りる必要があります。ひとりで全部やろうとせずに、まわりの人に相談してみてくださいね。
他の人に相談することが苦手なきぬまめは、若い頃、いつもひとりで全部やりきろうとしていました。
でも、「相談すること」は生きるためにとても重要なスキルだと今なら分かります。
なぜなら、相談することは相手と情報を共有することであり、助けてもらえる可能性が生まれ、自分に安心感が生まれるからです。
あなたは誰かに相談されたら、ほとんどの場合、嬉しくありませんか?
どうか、これを読まれている皆さんは「相談すること」「人に頼ること」を迷わないでください。
繊細さんが元気に生きるには?
著者の武田友紀さんご自身も繊細さんであり、ご自身に鞭打って働いていた会社員時代があったことが本書で綴られています。
その経験を活かし、HSPカウンセラーとしてご活躍されていらっしゃいます。
600名を超える繊細さんと出会われ、つくづく思うことは、「人は、自分のままで生きると元気だ」ということだそうです。
繊細さんが、自分のままで元気に生きる鍵。
それは、自分の本音ー「こうしたい」という思いを、何よりも大切にすることです。
きぬまめが自分の本音を大切にしないと大変なことになると思い知らされたのは、30代前半のことでした。
結婚して、夫の両親との同居話が持ち上がった時、自分の全力を振り絞って何年も抵抗したことは、繊細な自分にとって、今でも正解だったと思っています。
武田友紀さんは、また、以下のようにも述べています。
繊細さんは、自分の本音を大切にすることでたくましくなっていくのです。
自分の本音を大切にすることは、決してわがままではなく、自分の人生をたくましく生きていくために必要なことなのです。
自分の本音が分からないこともあると思います。そんな時はぜひこの本を手に取ってみてください。
ここには書ききれなかった、繊細さんが元気に生きる方法をたくさん見つけることができるでしょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
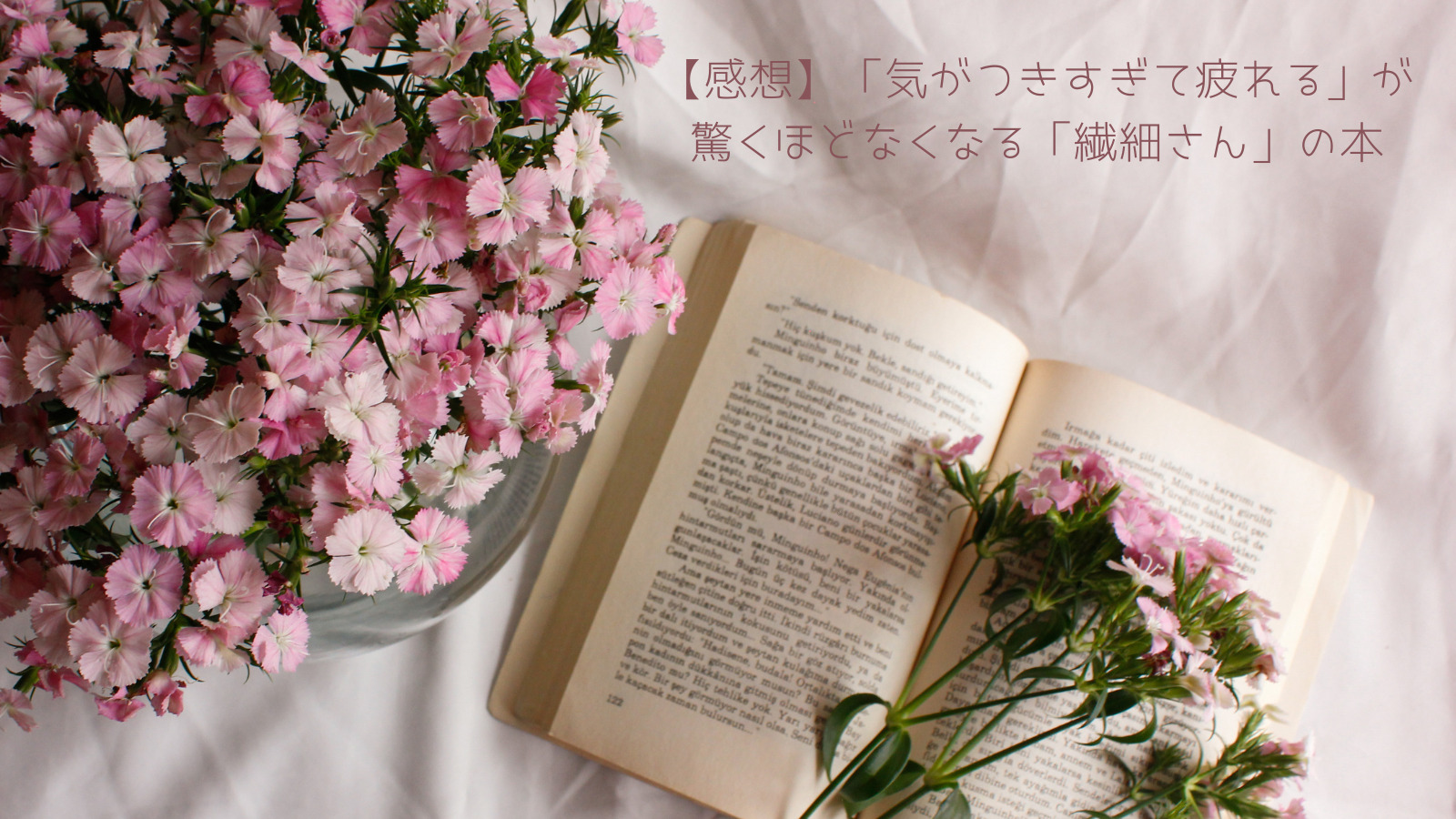


コメント